疲労・動けない|がんばりすぎた身体に【休む力】を取り戻す

「朝起きても疲れが取れない」「気力がわかず、何もしたくない」「身体が鉛のように重い」
そんな状態が続いていませんか?
一時的な疲れではなく、休んでも回復しない“慢性的な疲労”は、
身体のバランスが崩れ、エネルギー(気)の流れが滞っているサインです。
木氣治療室では、脈診や腹診を通して、身体がどこで止まっているのかを丁寧に見極め、
東洋医学的に“気・血・水”の巡りを整えながら、
再び「動ける身体」「笑顔で過ごせる日常」を取り戻すお手伝いをしています。
西洋医学からみた疲労・倦怠感
西洋医学では、疲労は身体的・精神的ストレスによるエネルギー消耗とされています。
睡眠不足、栄養不足、ホルモンの乱れ、自律神経の過活動などが重なり、
筋肉や神経の回復が追いつかず、「休んでも疲れが取れない」状態になります。
また、うつ状態や慢性疲労症候群、甲状腺機能低下症、鉄欠乏などが隠れている場合もあり、
検査で異常が見つからなくても、身体がSOSを出していることは多いのです。
西洋医学的な治療は、休養・栄養・投薬が中心ですが、
根本的な「気力の低下」や「回復力の落ち込み」には、
東洋医学的なアプローチが効果的なこともあります。
東洋医学でみる「動けないほどの疲れ」
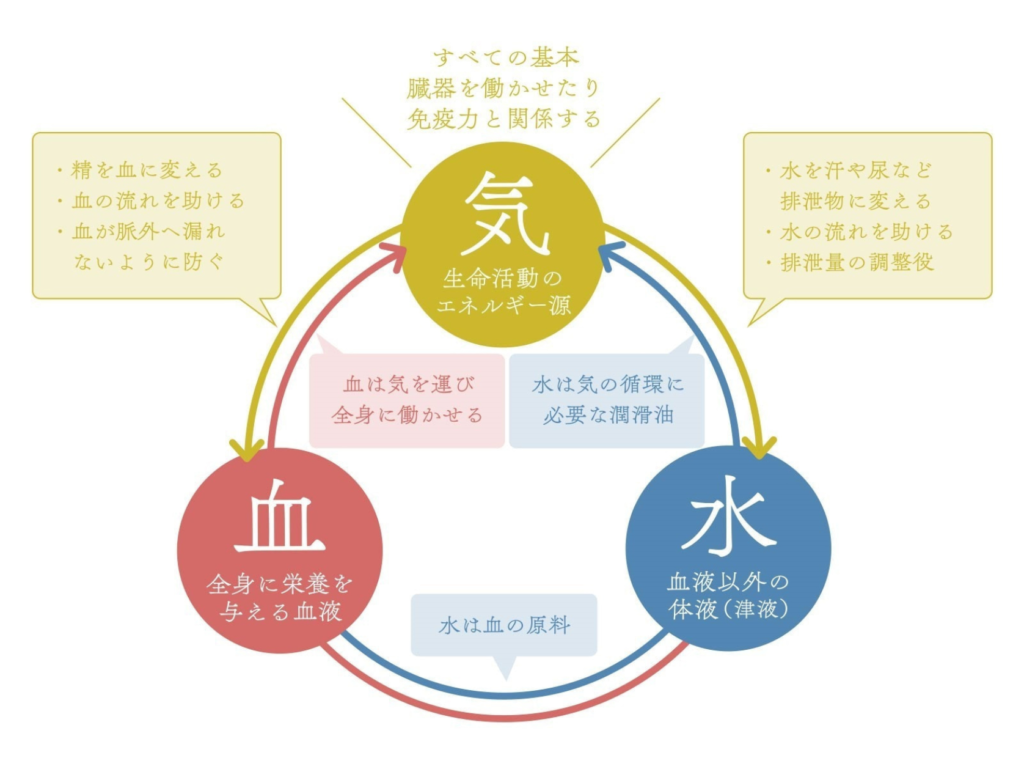
東洋医学では、疲労を「気・血・水」の不足や滞りととらえます。
特に「気」が不足すると、全身の働きが弱まり、まるで“エンジンが止まったような”状態になります。
主なタイプは次の通りです。
●気虚(ききょ)型
エネルギーそのものが不足し、倦怠感・息切れ・食欲低下などが起こる。
●脾虚(ひきょ)型
食べても栄養を作れず、身体を動かす力が出ない。胃もたれや下痢を伴うことも。
●腎虚(じんきょ)型
生命エネルギーが低下し、全身のだるさ・足腰の重さ・集中力の低下を感じる。
●気滞(きたい)型
ストレスで気の流れが滞り、イライラ・ため息・眠れない・疲れが抜けない。
●血虚(けっきょ)型
血が不足し、顔色が悪い・めまい・立ちくらみ・動悸などが出る。
このように、同じ「疲れ」でも原因は人によって違います。
だからこそ、脈や腹の状態をみて、その人だけの「疲労の根」を探ることが大切です。
鍼灸で回復力を取り戻す
鍼灸は、“気を動かし、血を巡らせる”ことで身体の自然な回復力を高めます。
① 自律神経の安定
鍼の刺激で交感神経と副交感神経のバランスを整え、
休息モードに入りやすい身体に導きます。
② 血流改善と酸素供給
血の巡りを良くして筋肉や脳への酸素供給を高め、疲れを抜けやすくします。
③ 気を補う
「気虚」体質の方には、脾・腎を補い、身体の芯からエネルギーを補充します。
④ 心身のストレス緩和
胸のつかえ・息苦しさ・不安・焦りなど、精神的疲労にも鍼灸が有効です。
鍼は浅くやさしく、痛みはほとんどありません。
施術中に「体がふっとゆるむ」「頭が軽くなる」と感じる方も多くいらっしゃいます。
五臓六腑からみた疲労の背景
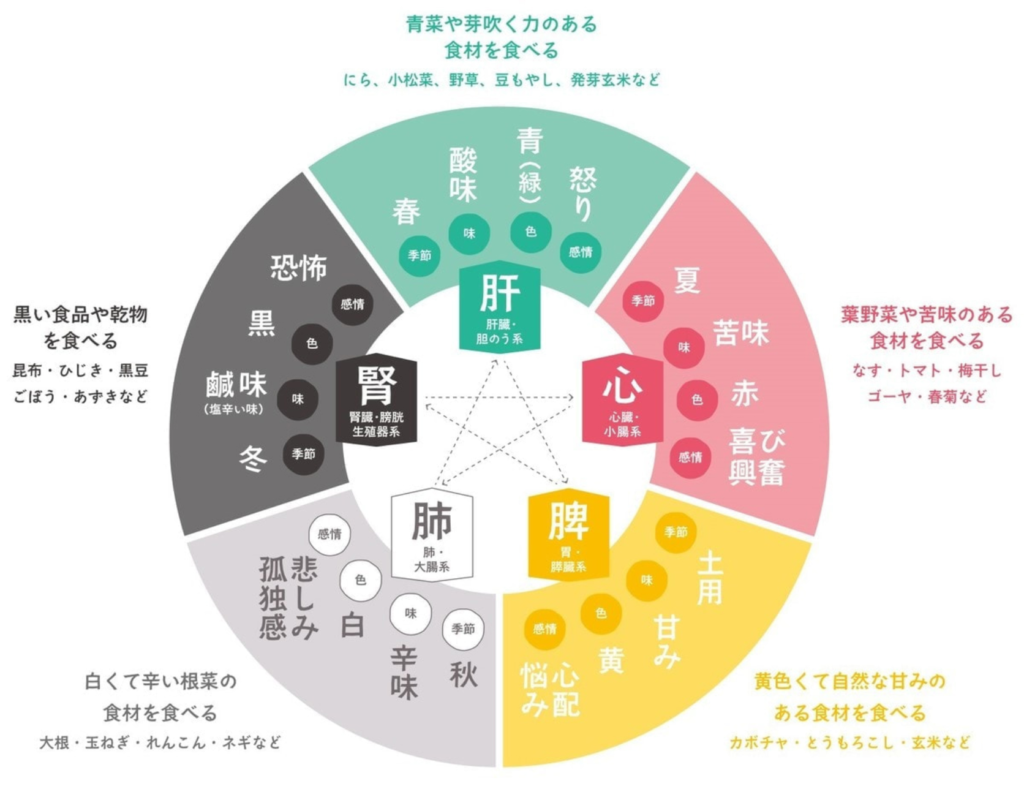
東洋医学では、疲れや無気力の背景には脾・肝・腎の働きが深く関わっています。
・脾:栄養を作り出す臓。脾が弱るとエネルギー不足になり、動けなくなる。
・肝:気の流れを調整し、ストレスを受け止める臓。肝が滞ると気持ちも身体も動かなくなる。
・腎:生命エネルギーの源。腎が弱ると全身の力が抜け、慢性疲労に。
鍼灸では、これらの臓腑を調和させることで、
「ただ休むだけでは回復しない疲れ」を、内側から整えていきます。
日常生活での養生法
疲労や無気力を改善するには、“がんばる”より“ゆるめる”ことが大切です。
● 睡眠を優先する
眠れない夜は無理に寝ようとせず、深呼吸やアロマで身体をゆるめることから。
● 食べすぎ・飲みすぎを控える
脾を守るためには腹八分目を意識。冷たい飲み物は控えましょう。
● 呼吸を意識する
ストレスで浅くなった呼吸を整えることで、気の流れがスムーズになります。
● 自然に触れる
太陽の光や風を感じることで、自律神経が整い、心身が回復しやすくなります。
木氣治療室の疲労回復治療

木氣治療室では、「ただ休んでも治らない疲れ」を東洋医学の視点から整えます。
脈診・腹診を通して、どの臓腑が弱っているかを確認し、
はり・お灸を使い分けて「気を補い・巡らせ・整える」施術を行います。
「体が重くて朝がつらい」「休日も動けない」「疲れがずっと取れない」
そんな方の多くが、数回の施術で「体が軽くなった」「呼吸が深くなった」と実感されています。
がんばり続けた身体に、“休む力”を取り戻してあげませんか?











