頭痛|薬に頼らず“頭の重さ”を根本から整える鍼灸

「頭がズキズキする」「天気が悪いと痛む」「薬を飲んでもまた痛くなる」
そんな頭痛に悩む方がとても増えています。
東洋医学では、頭痛は“頭だけの問題”ではなく、
身体全体の気・血の巡り、自律神経、ストレス、体質の乱れが関係していると考えます。
鍼灸では、痛みの原因を「めぐりの滞り」としてとらえ、
頭痛を抑えるのではなく、“痛みが起こらない身体”へと整えていきます。
西洋医学における頭痛の理解
西洋医学では、頭痛は大きく「一次性頭痛」と「二次性頭痛」に分類されます。
二次性頭痛は脳腫瘍やくも膜下出血など病気が原因のもので、緊急性があります。
一方、多くの方が悩むのは一次性頭痛であり、代表的なものに以下の3つがあります。
・緊張型頭痛:首や肩の筋肉がこわばることで起こる。長時間のデスクワークやストレスが原因。
・片頭痛:こめかみがズキズキと痛み、光や音に敏感になる。ホルモンや気圧の変化が関与。
・群発頭痛:目の奥が激しく痛むタイプ。男性に多く見られる。
西洋医学的な治療では、鎮痛薬や血管拡張抑制薬が用いられますが、
繰り返し薬を使用することで「薬物乱用頭痛」に陥ることもあります。
そのため、根本的に体質を整える東洋医学的アプローチが注目されています。
東洋医学における頭痛の理解
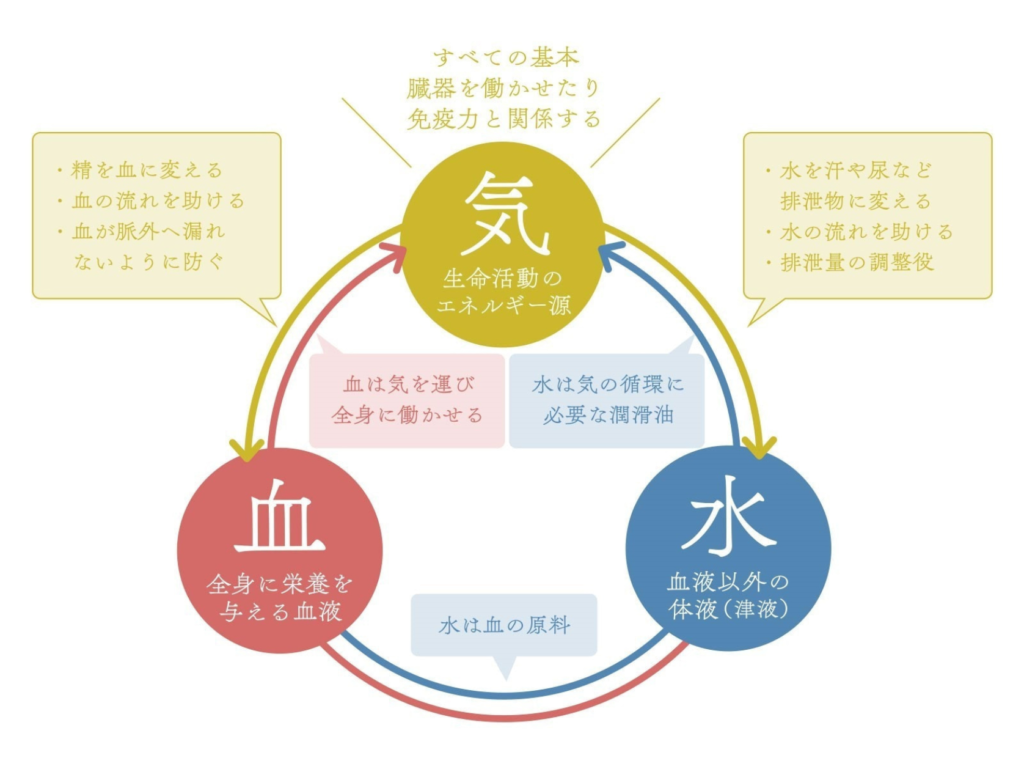
東洋医学では、頭痛は「気・血・水」の巡りや「五臓六腑」のバランスの乱れから生じると考えます。
・気滞(きたい)型:ストレスで気の流れが滞り、頭が締めつけられるように痛む。
・血虚(けっきょ)型:血が不足して頭に十分な栄養が届かず、ふらつきやボーッとする。
・肝火上炎(かんかじょうえん)型:怒りやストレスが溜まり、血圧が上がって頭が熱く痛む。
・痰湿(たんしつ)型:湿気や食べすぎによって体内に余分な水分が滞り、頭が重だるくなる。
つまり、同じ「頭痛」でも原因は人それぞれ。
木氣治療室では、脈やお腹を診ながら、あなたの体質に合わせた治療を行います。
鍼灸治療の効果とメカニズム
鍼灸治療は、自律神経・血流・筋肉・ホルモンのバランスを整えることで、
頭痛の根本改善をめざします。
1. 自律神経の調整
鍼刺激により副交感神経が優位となり、全身の緊張がゆるみます。
特に首や肩の筋肉が柔らかくなることで、緊張型頭痛に効果的です。
2. 血流の改善
鍼で頭部・頸部・背中の血行を促進することで、酸素不足による痛みを軽減します。
3. ホルモンバランスの安定
月経前後の頭痛や片頭痛には、ホルモンの変化が関係しています。
鍼灸は内分泌系に働きかけ、女性ホルモンのリズムを整えます。
4. 痛みの感受性を下げる
鍼刺激によりエンドルフィンが分泌され、痛みの感じ方が和らぎます。
五臓六腑との関係(肝・脾・腎・心)
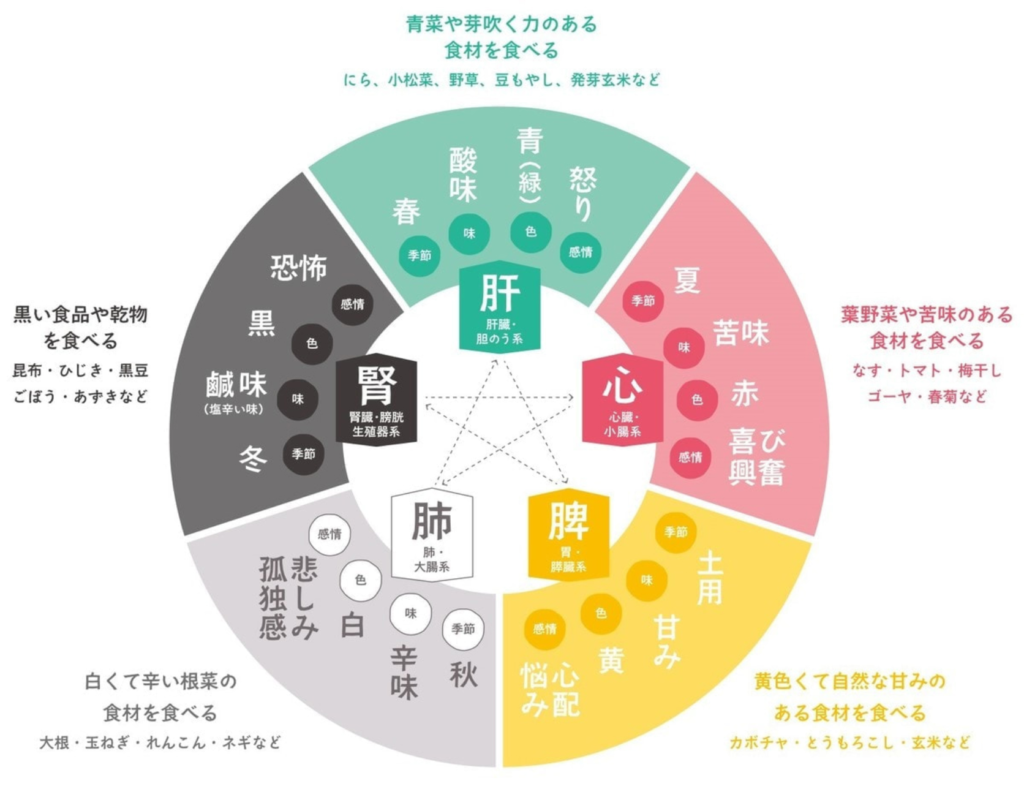
東洋医学では、頭痛は五臓の乱れと深く関係しています。
・肝:ストレスや怒りで気が上昇し、頭に熱がこもって痛む。
・脾:食べすぎ・疲労によりエネルギーが不足し、重だるい頭痛を起こす。
・腎:加齢や疲労によって腎精が減り、慢性的な頭の重さが続く。
・心:不安や緊張により動悸・不眠を伴う頭痛を引き起こす。
これらの臓腑を整えることで、「痛みを生まない身体」を育てていきます。
日常生活での養生法
鍼灸治療に加え、日常のセルフケアでも頭痛は大きく改善します。
●冷やしすぎ・温めすぎに注意
首や頭を冷やしすぎると血流が悪化し、頭痛を招きます。
寒い季節は首を温め、夏は冷房に注意しましょう。
●パソコン・スマホの使いすぎを控える
眼精疲労は頭痛の原因です。1時間に一度は目と肩を休めましょう。
●深呼吸でリラックス
ストレスによる頭痛には、1日数回の深呼吸が効果的です。
●睡眠リズムを整える
寝不足も寝すぎも頭痛を悪化させます。一定のリズムで休むことを意識しましょう。
木氣治療室でできること

木氣治療室では、頭痛を「身体全体の巡りの乱れ」として捉え、
脈診・腹診・舌診を通じて、根本原因を丁寧に見極めます。
鍼はごく浅く、痛みを感じにくい施術で、
首・肩・背中・頭部を中心に「気血の流れ」を整えます。
「薬に頼らず、自然に軽くなりたい」
そんな方に、東洋医学の鍼灸はとても有効です。
痛みを抑えるだけでなく、
“痛みを生まない身体”を一緒に育てていきましょう。











